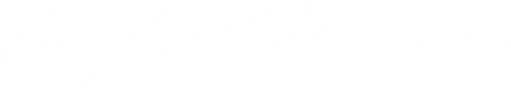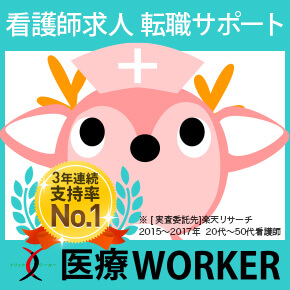「子どもが好き!」という方に人気の小児科看護師。
しかし、子どもは大好きなのに、子どもへの接し方に悩んでいる・・・という方も多いのではないでしょうか?
院内で、子どもと多くの時間を過ごす看護師。よりよい看護のためには、子どもとのコミュニケーションは必要不可欠です。
今回は4つのテーマから、子どもとの接し方のヒントをご紹介します。
話し方で、伝わり方は変わる

子どもとの話し方で気をつけたいことは、
◎ ゆっくりとしたスピード
◎ 大きすぎず、また小さすぎない声量
◎ はきはきと話す
◎ 子どもに目線を合わせる
◎ 子どもが安心するような笑顔
病院の雰囲気やにおい、見慣れない大人たち、初めての注射・・・
子どもは病院にいる間、たくさんの不安と戦っています。
子どものペースに合わせた話し方を心がけることで、「あなたの味方だよ」という気持ちを伝えることができます。
また子どもに対しての、
× 上から目線
× 難しい医療用語
これらは、子どもへの不安を大きくしてしまいます。
伝えるべきことは、子どもにも分かる言葉で、同じ目線に立って話すことが大切です。
好きなものを知れば、会話が生まれる

コミュニケーションを取る上で、子どもが興味を持つものを知っていることは小児科看護師にとって大きな強みになります。
小児科に来院する子どもは、一般的に新生児から中学生です。
子どもに人気があるのはやっぱりアニメ。
ここでは、年代別の人気ランキングをご紹介します。
好きなキャラクターランキング
●男子TOP5(0~12歳)
1位 妖怪ウォッチ 17.5%
2位 きかんしゃトーマス 10.5%
3位 それいけ!アンパンマン 8.3%
4位 ドラえもん 7.8%
5位 仮面ライダーシリーズ 6.0%●男子0~2歳TOP3
1位 きかんしゃトーマス 29.0%
2位 それいけ!アンパンマン 27.0%
3位 いないいないばあっ! 9.0%●男子3~5歳TOP3
1位 仮面ライダーシリーズ 15.0%
2位 きかんしゃトーマス 13.0%
3位 スーパー戦隊シリーズ 10.0%
3位 妖怪ウォッチ 10.0%●男子6~8歳TOP3
1位 妖怪ウォッチ 34.0%
2位 ポケットモンスター 11.0%
3位 仮面ライダーシリーズ 8.0%●男子9~12歳TOP3
1位 妖怪ウォッチ 25.0%
2位 ドラえもん 16.0%
3位 ドラゴンボールシリーズ 11.0%●女子TOP5(0~12歳)
1位 それいけ!アンパンマン 15.0%
2位 プリキュアシリーズ 8.8%
3位 妖怪ウォッチ 6.3%
3位 アナと雪の女王 6.3%
5位 すみっコぐらし 5.5%
5位 ディズニープリンセス 5.5%●女子0~2歳TOP3
1位 それいけ!アンパンマン 45.0%
2位 いないいないばあっ! 16.0%
3位 しまじろう 7.0%●女子3~5歳TOP3
1位 プリキュアシリーズ 19.0%
2位 それいけ!アンパンマン 14.0%
3位 ディズニープリンセス 11.0%
3位 アナと雪の女王 11.0%●女子6~8歳TOP3
1位 プリキュアシリーズ 13.0%
2位 妖怪ウォッチ 12.0%
3位 すみっコぐらし 8.0%●女子9~12歳TOP3
1位 すみっコぐらし 14.0%
2位 リラックマ 12.0%
3位 妖怪ウォッチ 7.0%
とは言っても、子ども一人ひとりによって興味のあるものは異なります。
人気のあるアニメの知識を蓄えておきつつ、
・子どもの持ち物はどのキャラクターのものが多いのか
・院内にあるもので、子どもは何に興味を持って視線を向けているのか
これらに気を配り、常にアンテナを張って、子どもの好奇心の対象を探すことが大切です。
また情報収集のために、保護者の方からお話を聞くことも効果的です。
子どもからのサインを受け取る

子どもは絶えず、周囲に対してサインを送っています。
そのサインは言葉とともに発せられたり、あるいはしぐさや態度だけで示されます。
言葉のないサインも、大切なコミュニケーションのひとつ。
・指をしゃぶる、爪を噛む ・・・不安や寂しさの表れ
・噛みつく ・・・心を落ち着かせてほしい
・無表情 ・・・自分の気持ちを抑えている
このようなサインを受け取った時は、無理に言葉を引き出そうとするのではなく、子どもが安心できるような環境づくりを心がけましょう。
・あごを引いて睨みつける ・・・敵対心の表れ
これは子どもが何かに納得できず、イライラしているときのサインです。
何が子どもに不快感を与えているのか、要因を探すことが大切です。
「聞き方」にも工夫を

子どもに対する話し方と同じくらい、話を聞くことは難しく、重要なものです。
せっかく子どもが話をしてくれても、聞き方次第では拒絶感を与えてしまいます。
いつもの聞き方に少しの工夫を加えることで、子どもが何倍も話したくなる空気をつくることができます。
・子どもに向き合い、真剣に聞く
「自分の話を聞いてくれている」という安心感につながります。
『ながら聞き』や、目線を合わせないという態度は子どもを不安にさせてしまいます。
・あいづち > コメント
自分の意見で話の腰を折らず、相槌を打って言葉を発しやすい空気をつくります。
・共感を伝える4つの方法
1、うなずき ・・・ 少しオーバーにするくらいがベスト。
2、オウム返し ・・・
(例)子ども「今日○○して、すっごく楽しかった!」
あなた「そっか、○○して楽しかったんだね~」
3、言い換え ・・・
(例)子ども「昨日△△ちゃんとおままごととお絵描きしたの!」
あなた「そうなんだ!△△ちゃんとたくさん遊べたんだね!」
4、子どもの気持ちに名前をつける
(例)子ども「明日ママとお出かけするの!」
あなた「そうなんだ、それは楽しみだね!」
子どもが、話した話題に対してどんな気持ちを持つのかを想像し、言葉にします。
この4つを組み合わせることで、「私の話をちゃんと聞いてくれている!」と子どもは共感を感じることができます。
・否定しない
言葉を返すとき、「でも」「だって」をついつい使ってしまう人は多いのではないでしょうか?
話を否定されると、悲しい気持ちになるのは大人も子どもも同じです。
子どもが表すどのような感情も、否定せずに話を聞くよう意識しましょう。
大切なのは、向き合う姿勢

この記事を読んでくださった皆さんは、「もっと子どもと関わりたい。よい接し方を知りたい。」という小児科看護師の方が多いと思います。
その子どもに向き合おうという姿勢は、きっと子どもたちに伝わっているはず。
今回ご紹介したテクニックは、全て今すぐに実践できるものばかりです。
子どもへの気持ちと、接し方のテクニックを合わせれば、子どもとのコミュニケーションを今よりも楽しめると思います。