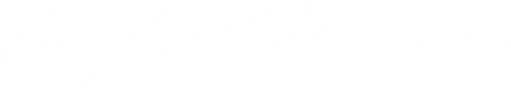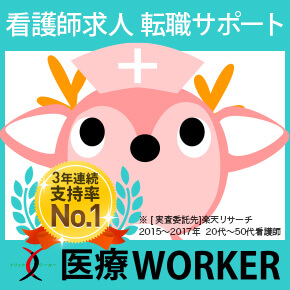節分は、家族を鬼から守り、家に福が来るように“豆まき”を行う習慣があります。
大事な家族行事のひとつですが、入院している患者さんは自宅で豆まきを行うことができません。
近年では、そんな患者さんのために院内レクレーションの一環として、節分イベントを開催している病院が増えてきています。
今回は、患者さんがより楽しめるイベントにするための情報をまとめましたので、ぜひご覧ください!
どうして節分に豆まきをするの?

昔から「節分は豆まきをするもの」と、なんとなく過ごしてきた人がほとんどかも知れませんが、実際に「なぜ豆まきをするのか」意味を理解した上で行事に取り組めば、より中身の濃いレクレーションになります。
さっそく節分に豆まきを行う理由をみていきましょう。
節分というのは「季節の変わり目」を意味しており、昔からこの時期には鬼が出ると言われています。
鬼という魔物を滅ぼす意味で「魔滅(まめ)」が使われるようになりました。
また、豆まきの豆は必ず炒った豆を使います。
「炒る」という言葉を「射る」にかけていて、「魔目(鬼の目)を射る」ともいわれています。
他にも、「鬼が暴れているときに、ある村人が神のお告げを聞き、鬼の目をめがけて豆を投げた」ことがきっかけなど、いろいろな説があります。
小児科など小さい子どもが多い病棟であれば、紙芝居にまとめてみても良いですね。
豆まきにはルールがある
豆まきを行うようになった由来に基づいて、豆まきにはルールがあります。
鬼を追い払うための行事なので、豆まきは鬼がくる夜に、家の主または年男・年女が代表して行います。
掛け声は地域によって異なりますが、外に向かって「鬼は外」と言いながら2回豆をまき、鬼が戻ってこれないように窓をすべて締め切ってから「福は内」という掛け声とともに2回部屋に豆をまきます。
苗字に「鬼」という漢字が入っている家庭では「福は内」「鬼は内」「悪魔(は)外」と言うところもあるようです。
名前に「鬼」の字が入っている患者さんがいる場合は考慮してあげると良いでしょう。
院内レクレーションとして節分を楽しむ方法
先ほど豆まきのルールについて説明しましたが、病院で節分行事を開催するなら、代表者1名が豆まきを行うのではなく、参加した患者さんひとりひとりが楽しめるようなミニゲーム等があれば良いと思いませんか?
例をあげておきますので参考にしてみてくださいね。
みんなで節分の飾り付け♪

◆準備するもの
・折り紙
・スティックのり
・セロハンテープ
・はさみ
お多福と鬼を折り紙で作成し、それぞれが作った鬼たちを壁に飾るだけでも十分節分の雰囲気を味わうことができます。
余った折り紙は、長方形に切って輪っかを作り、連ねて飾りにしても良いでしょう。
折り方については、わかりやすい動画をみつけたので紹介させていただきますね。
鬼は外!チーム対抗★鬼退治ゲーム

◆ルール
鬼をイメージして作った的にむかって、豆に見立てた玉を投げます。
的に当たった場所によって得点を決め、チーム別で総合点を競うゲームです。
ダーツをイメージするとわかりやすいかもしれません。
◆準備するもの
鬼の的
・色画用紙
・ハサミ
・スティックのり
・両面テープ
豆に見立てた玉
・色画用紙
◆作り方
1.色画用紙を鬼の形に切り取る(胴体部分の面積が大きくなるように作ると良い)
2.鬼の胴体部分に的の絵を描く(玉が当たった場所に応じて点数がわかるように数字も書いておく)
3.鬼の胴体全体に両面テープを貼る
4.余った画用紙を細かくちぎり適当に丸める(投げた時に鬼の胴体にくっつきやすいように平らな面ができるように丸めることがポイント)
両面テープを貼っておいた鬼の高得点エリアにくっつくようにやさしく玉を投げるのがコツです。
簡単なゲームですが、意外と盛り上がっておすすめですよ♪
玉の入れ物については、折り紙などで小箱を用意しておけばより一層、節分の雰囲気を楽しめますね!
まとめ
節分に豆まきをする理由と、患者さんみんなが楽しめるレクレーションを紹介させていただきましたが、いかがでしたか?
毎日を病院で過ごす患者さんにとって、節分は季節を感じるための大事な年間行事のひとつです。
今回の内容を参考に、思い出に残る1日にしてあげてくださいね♪