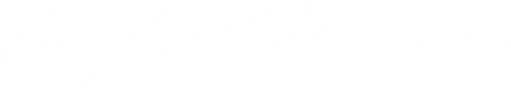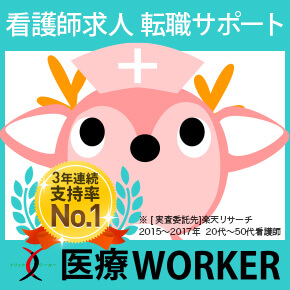お正月のゆっくりした雰囲気からいつも通りの日常に戻ってきて、そろそろお正月の飾りを片付けていかなければならない時期ですね。
その片付けの一環でもある“鏡開き”ですが、お年寄りの多い病院や介護施設で行う際にはいくつか注意が必要です。
今回は、看護師が知っておくべき”鏡開き”についてのあれこれをまとめてご紹介します!
そもそも“鏡開き”は必要?
昔からお正月に飾っていた鏡餅は、鏡開きの際に食べるという風習があります。
鏡餅は、年神様をお迎えするためのものとされており、お正月から松の内までは鏡餅に年神様が宿っているといわれており、松の内は、関東では1月11日、関西では1月15日と時期が異なります。
よって、神様が帰られた1月11日または1月15日以降に鏡開きを行うのが一般的です。
神様の力が宿った鏡餅をみんなでいただくことに今年1年の無事や健康を祈る意味が込められているのです。
お餅を食べなかったからといって「縁起が悪い」や「バチが当たる」などの言い伝えはありませんが、年間行事のひとつとして実施すれば利用者さんも喜び、施設内も活気づくでしょう。
鏡開きの注意点とは?
鏡開きを行う際、一体どのような点に注意しなければならないのか。
3つの項目に分けてご紹介します。
1・包丁は使わないこと

鏡開きでお餅を分ける際、包丁で切ったほうが便利だと思う方も多いのではないでしょうか。
しかし「切る」という作業は「切腹」を連想させてしまうためNGです。
また、神様との縁を切ってしまうと言われていることも、包丁(刃物)を使ってはいけない理由のひとつです。
鏡餅は木槌などを使って割って開くようにしましょう。
また、最近では鏡餅の形をした入れ物にお餅が小分けに入った商品も販売されていますが、そのようなお餅はお年寄りにとっては少し大きいため、病院や介護施設で行う鏡開きに使用されることは少ないようです。
2・お年寄りが食べているときはあまり話しかけない

これは鏡開きにかかわらず、普段から食事介助を行っている看護師にとっては当たり前のことかもしれませんね。
お正月の楽しい雰囲気でおしゃべりしながら食べたくなる気持ちはわかりますが、「食べる」行為と「喋る」行為の同時並行は、お年寄りにとって難易度の高いことです。
食べ物を口に含んでいるときは、こちらから話しかけたり返事を急かすようなことがないように注意が必要です。
もし、相手が話したいときには食事介助の手をとめて、ゆっくり話を聞いてあげるようにしましょう。
3・お年寄りが食べやすいように工夫したレシピを

お餅は噛み切ることが難しく、のどに詰まらせてしまう危険性が高いため、一口サイズにして調理しましょう。
あえてお餅を使わずに、他の食材で代用した料理もいくつかありますので紹介しておきます。
施設によっては活用が難しい場合もあるかもしれませんが、ぜひ参考にしてみてくださいね!
まとめ
病院や介護施設など、お年寄りのいる場所での鏡開きについて紹介してきましたがいかがでしたでしょうか。
昔からある風習を大事にすることで、病院や施設を利用するお年寄りの方に季節を感じてもらうことができます。
勤務している側としても、季節を感じながらいきいきと過ごしてくれる利用者さんを見ると業務の励みになりますよね。
忙しい毎日だからこそ、このような年間行事は大切にしていきたいものです。